- HOME
- 男性不妊症について
- 乏精子症
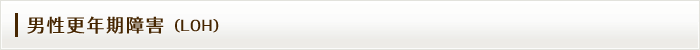
潜在的な患者数が多いと言われる、男性更年期障害について解説します。
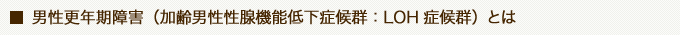
更年期障害というと女性特有の疾患と考えられていますが、実は男性にも同様の症状が存在します。
欧米では30年以上も前から男性更年期障害が注目されています。わが国で注目されるようになったのは、はらたいらさんがご自身の体験を本にされ、マスメディアがこの男性更年期障害を頻回に取り上げられてからです。
マスメディアや一般社会での関心が高い理由として、先進国の多くが高齢化社会を迎えつつあること、疾患の概念が目新しく潜在的な患者数が多いことが考えられます。
男性更年期障害は様々な因子が複雑に絡み合って引き起こされるもので、その因子の一つが加齢に伴う男性ホルモンの低下(加齢男性性腺機能低下症候群:LOH症候群)と考えられています。
そもそも男性には女性のような明確な更年期の定義(女性更年期は性成熟状態から卵巣機能が完全に消失するまでの期間)はなく、女性のこの期間にみられる心身のさまざまな障害、すなわち更年期障害が男性にみられるかというと必ずしもそうではないことから、男性には更年期障害はないと思われていました。しかし男性にも女性にみられるような特徴的な症状はないにしても、多かれ少なかれ、何らかの症状が見られることが多いことがわかってきました。ただ男性の場合、女性のように急激なホルモンの低下はないことが女性のように激しい症状が出ない理由と考えられています。
このように男性ホルモンの低下が原因であることから、正式名称は「加齢男性性腺機能低下症候群:LOH症候群」とされていますが、用語としては「男性更年期障害」が一般的に定着しています。

主要な症状は以下の7つとされています。
- リビドー(性欲)と勃起の質と頻度、とりわけ夜間睡眠時勃起の減退
- 知的活動、認知力、見当識の低下および疲労感、抑うつ、短気などに伴う気分変調
- 睡眠障害
- 筋容量と筋力低下による除脂肪体重の減少
- 内臓脂肪の増加
- 体毛と皮膚の変化
- 骨減少症と骨粗鬆症に伴う骨塩量の低下と骨折のリスク増加
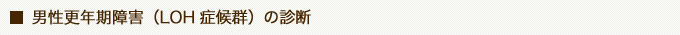
まずご自分でやってみられるなら以下のMorleyの質問が簡単でいいでしょう。
- 性欲(セックスしたい気持ち)の低下がありますか?
- 元気がなくなってきましたか?
- 体力あるいは持続力の低下がありますか?
- 身長が低くなりましたか?
- 「日々の楽しみが少なくなった」と感じていますか?
- 物悲しい気分、怒りっぽいですか?
- 勃起力の低下を実感しますか?
- 最近運動する能力が低下したと感じていますか?
- 夕食後うたた寝をすることがありますか?
- 最近仕事の能力が低下したと感じていますか?
以上の質問に対して、
(1. )か(7. )に当てはまるか、あるいは
その他の3項目以上に当てはまる場合、男性更年期障害(LOH症候群)が疑われます。
診断は主に問診および男性ホルモン検査で行います。
-
問診票
Aging males’ symptoms(AMS)スコア
M.I.N.I
IIEF5(国際勃起機能スコア)
IPSS(国際前立腺症状スコア)
これら問診票により、症状の程度を確認し、うつ病などの鑑別診断を行います。
-
遊離型(フリー)テストステロン
男性更年期障害(LOH症候群)の診断には血液中の男性ホルモンの測定が必須です。男性ホルモン(テストステロン)にはいくつかの種類がありますが、
遊離型(フリー)テストステロンが診断に最も信頼できる指標であるとされています。
遊離型(フリー)テストステロンが8.5pg/ml未満なら男性ホルモンが明らかに低いと判断し、8.5pg/ml以上から11.8pg/ml未満なら男性ホルモンが低下傾向にあると判断します。
この遊離型(フリー)テストステロンは日内変動があるため午前中の採血による検査が必要です。
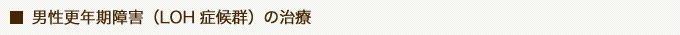
男性更年期障害(LOH症候群)の治療は男性ホルモンの補充が中心となります。
男性ホルモン補充を行うかどうかは遊離型(フリー)テストステロンの値で決めます。
遊離型(フリー)テストステロンが、
- 8.5pg/ml未満であれば男性ホルモンの補充を第一に行います。
- 8.5pg/ml~11.8pg/mlなら病状の程度や治療の有用性/リスクを検討し男性ホルモンの補充を行うか判断します。男性ホルモンの補充を3ヶ月間行い症状が改善するかをみてみるのも有用な方法です(治療的診断といいます)。
- 11.8pg/ml以上なら男性ホルモンの補充は行わず、他の治療(症状に応じた治療)を選択します。
男性ホルモンの補充療法としては、
- 男性ホルモン注射(2~3週毎に1回)
- 胎盤性性腺刺激ホルモン(hCG)注射(週に1~2回)
- 男性ホルモン軟膏塗布(1日に1~2回)
男性ホルモン補充療法の副作用として多血症(血液が濃くなる)、睡眠時無呼吸、女性化乳房、ニキビ、体液の増加が出現することがあります。また男性ホルモンは前立腺肥大・前立腺癌の進行を早める作用があると考えられるため定期的な検査が必要です。
このため男性ホルモン補充療法を開始した場合、最初の1年間は3ヶ月毎に診察、体重測定、血液検査、ホルモン検査、PSA検査(前立腺癌の検査)、心電図を受ける必要があります。
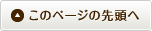

【触診検査】

診察では、オーキドメーター(プラスチックでできた型抜き)を陰嚢の皮膚の上からあてて精巣サイズを測ります。
精巣を触ったときの硬さも重要で、小さくて柔らかい精巣は精子を作る働きが弱いとされています。
次に、精巣上体(副睾丸)と精管も触らせていただき、腫れていたり、押えて痛みがないかを調べます。
男性不妊症の原因となる精索静脈瘤がないか陰嚢上部を観察し、触らせていただきますが、立ったり、いきんで下腹に力を入れていただいたりして、安静に寝ている時との比較をします。
外陰部の診察は恥ずかしいし、あまり気持ちの良いものではないでしょうが、痛みなどの苦痛をともなうものではありませんので心配いりません。

【精液検査】

【超音波検査】
超音波検査(エコーともいいます)はタバコの箱のような探触子(プローブともいいます)を陰嚢に当てるだけで精巣(睾丸)がモニター上に描出され、痛くもかゆくもない検査です。
まず、精巣の上下、前後、左右の径を計り、体積を計算します。精巣内部にかたまり(精巣腫瘍)や小さな結石(微小結石)がないかを確認し、精巣の外にある精巣上体(副睾丸)や精管も詳しく観察します(精子の通り路に詰まりがあると、精巣上体や精管が拡張します)。
精索静脈瘤があると、内精索静脈が拡張して描出され、カラードプラ法では血液の逆流をカラーで見ることができます。

【内分泌検査】
血液中の卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)、プロラクチン(PRL)、テストステロンを測定します。
卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)は脳の下垂体前葉から分泌されるホルモンで、性腺刺激ホルモンと呼ばれます。FSHは精巣(睾丸)のセルトリ細胞に働いて、精子の形成を促進し、LHはライディッヒ細胞に作用して、テストステロン(男性ホルモン)の合成を促します。分かりやすくいうと、FSHは精子を作らせるホルモンで、LHは男性ホルモンを作らせるホルモンです。
プロラクチン(PRL)はFSHやLHと同様に下垂体前葉から分泌され、産褥期に乳汁分泌を促進する働きがあります。男性でPRLが過剰に分泌されると、性欲や性腺機能の低下をきたすことが知られています。
これらのホルモンの値から、いろいろな病気のパターンを推測しますが、FSHが著明に上昇していれば精子を作る働きに問題があるのは間違いありません(精巣の精子を作る働きが悪いため、それをなんとかしようとFSHが増えていると考える)。

【遺伝子検査】
精路の閉塞所見がない無精子症や高度の乏精子症(500~1,000万個/ml以下)の患者さんは、遺伝的な異常を伴うことがあり、遺伝学的検査(染色体検査、遺伝子検査)を受ける必要があります。
男性不妊症の約7%に染色体検査で異常がみられるとされています。その頻度は精子数が少ないほど高くなり、無精子症の患者さんでは10~15%に染色体異常がみられるのに対し、乏精子症では5%、正常男性では1%以下です。染色体異常の2/3は通常[46、XY](染色体検査=正常)よりX染色体の数が多いクラインフェルター症候群[47、XXY](染色体検査=クラインフェルター症候群)ですが、その他に染色体の構造異常も見つかります。
遺伝子検査が進歩して、従来の染色体検査では見つけられなかった遺伝子異常が診断できるようになり、無精子症や高度の乏精子症の患者さんの10~15%ではごくわずかにY染色体の一部が欠けている(microdeletion=微小欠失)ことが明らかとなりました(遺伝子検査=DAZ欠失なしとあり)。以前はこれらの異常はお子さんに伝わることはありませんでしたが、顕微授精(ICSI)で男児を授かられるとお父さんと同じように不妊症になる可能性が非常に高いと考えられます。
染色体や遺伝子の異常が見つかった場合は、顕微授精の前にカウセリングを受けられるのが良いでしょう。
*嚢胞状線維化症では非常に高率に先天性両側精管欠損症を合併することが知られています。さらに嚢胞状線維化症がCFTR遺伝子の異常によることが明らかとなり、欧米では先天性両側精管欠損症の患者さんはCFTR遺伝子の検査を受けることが推奨されています。しかし、日本人ではこの病気は非常に少ないため、わが国ではCFTR遺伝子の検査は一般には行われていません。

【薬物治療】
手術や心理療法など様々な治療がありますが、そのなかで薬物を患者さんに投与する治療法になります。
病気の治癒、患者さんのQOL(生活の質)の向上を目指す治療法です。
薬は主にクロミフェン、漢方薬、ビタミン剤、カリクレインなどです。薬物治療により精子数の増加や運動率の改善が期待できます。またこれらの薬は精子の質を改善させることがわかってきました。精子の質が改善すれば受精率、妊娠率が上がります。

【ホルモン治療】
各種症状に対してホルモン剤、あるいはホルモンの分泌を促進または抑制する薬剤を用いる治療法になります。
定期的に投与する場合が多く、期間も長くなることがあります。
最新のホルモン治療として無精子症に対する治療があります。
無精子症でホルモン治療を行い精子が出現したという報告や、micro(MD)-TESEで精子が見つからず、ホルモン治療後に再度micro(MD)-TESEを行い精子が見つかったという報告が出てきました。

【精索静脈瘤手術】

精索静脈瘤を手術すると自然妊娠のチャンスが2.8倍高くなるなど、男性不妊患者さんにおける精索静脈瘤手術の治療効果は明らかです。
また、無精子症の患者さんでも、精索静脈瘤を手術すると20~30%で精液中に精子がみられるようになったとする報告があります。
当院での精索静脈瘤手術は日帰りで行っております。
例えば、朝10時に来ていただいて、お昼過ぎには歩いて帰っていただきます。
手術当日はゆっくり安静にしていただきますが、じっと寝ておく必要はありません。
手術翌日は傷を見せにご来院いただきますが、みなさん通常通りにお仕事をされています。

【顕微鏡下精巣内精子回収術】

当院では「micro(MD)-TESE(顕微鏡下精巣内精子回収術)」などの高度先端医療に取り組んでおります。精子をつくる機能は正常に働いているにも関わらず、精子を運ぶ管が詰まっていて精液中に混ざらない場合や、造精機能が低い場合も、micro(MD)-TESEによって精巣に精子が見つかりさえすれば、顕微授精が可能になります。TESEとは陰嚢を0.5~1.0cmほど切開し精巣内の精細管と呼ばれる小さな組織を採取する方法です。micro(MD)-TESEは手術用顕微鏡下に精細管を採取する方法で、精子の採取率が高く、負担も少ない手術です。当院ではmicro(MD)-TESEを日帰りで行っています。手術当日はゆっくり安静にしていただきますが、じっと寝ておく必要はありません。手術翌日は傷を見せにご来院いただきます。




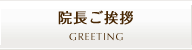



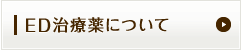
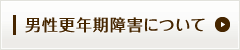
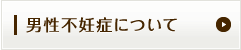
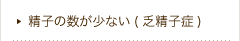
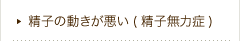
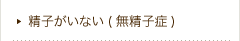
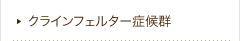
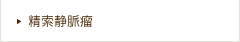
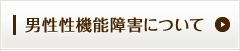
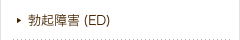
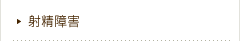
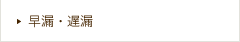

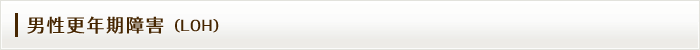
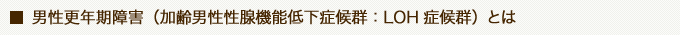

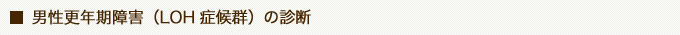
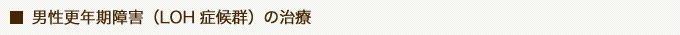
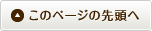

 診察では、オーキドメーター(プラスチックでできた型抜き)を陰嚢の皮膚の上からあてて精巣サイズを測ります。
診察では、オーキドメーター(プラスチックでできた型抜き)を陰嚢の皮膚の上からあてて精巣サイズを測ります。 精液検査は、男性不妊症の診断・治療において最も基本となるものです。当院では、WHO精液検査ラボマニュアル第5版(2010年)に準拠して詳細な精液検査を行っています。
精液検査は、男性不妊症の診断・治療において最も基本となるものです。当院では、WHO精液検査ラボマニュアル第5版(2010年)に準拠して詳細な精液検査を行っています。 精索静脈瘤を手術すると自然妊娠のチャンスが2.8倍高くなるなど、男性不妊患者さんにおける精索静脈瘤手術の治療効果は明らかです。
精索静脈瘤を手術すると自然妊娠のチャンスが2.8倍高くなるなど、男性不妊患者さんにおける精索静脈瘤手術の治療効果は明らかです。 当院では「micro(MD)-TESE(顕微鏡下精巣内精子回収術)」などの高度先端医療に取り組んでおります。精子をつくる機能は正常に働いているにも関わらず、精子を運ぶ管が詰まっていて精液中に混ざらない場合や、造精機能が低い場合も、micro(MD)-TESEによって精巣に精子が見つかりさえすれば、顕微授精が可能になります。TESEとは陰嚢を0.5~1.0cmほど切開し精巣内の精細管と呼ばれる小さな組織を採取する方法です。micro(MD)-TESEは手術用顕微鏡下に精細管を採取する方法で、精子の採取率が高く、負担も少ない手術です。当院ではmicro(MD)-TESEを日帰りで行っています。手術当日はゆっくり安静にしていただきますが、じっと寝ておく必要はありません。手術翌日は傷を見せにご来院いただきます。
当院では「micro(MD)-TESE(顕微鏡下精巣内精子回収術)」などの高度先端医療に取り組んでおります。精子をつくる機能は正常に働いているにも関わらず、精子を運ぶ管が詰まっていて精液中に混ざらない場合や、造精機能が低い場合も、micro(MD)-TESEによって精巣に精子が見つかりさえすれば、顕微授精が可能になります。TESEとは陰嚢を0.5~1.0cmほど切開し精巣内の精細管と呼ばれる小さな組織を採取する方法です。micro(MD)-TESEは手術用顕微鏡下に精細管を採取する方法で、精子の採取率が高く、負担も少ない手術です。当院ではmicro(MD)-TESEを日帰りで行っています。手術当日はゆっくり安静にしていただきますが、じっと寝ておく必要はありません。手術翌日は傷を見せにご来院いただきます。